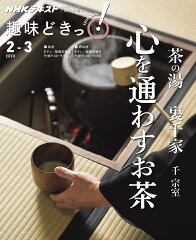茶道って作法はたくさんあるけど、たくさんおしゃべりはしないよね!
なんだか黙々と事が進んでいくっていうイメージがあるよ。
なんであのスタイルが変わらず引き継がれているんだろう。。。
日本には、「言葉を交わさずコミュニケーションを取る」ことに関することわざや言葉があります。
・空気を読む
・阿吽の呼吸(あうんのこきゅう)
・雄弁(ゆうべん)は銀(ぎん)沈黙(ちんもく)は金(きん)
それぞれ、日本特有の価値観を表していて、日本人のコミュニケーションのあり方の1つでもあります。
そして、それは日本の茶道の作法にもみられます。いや、むしろ、長い歴史の中での日本の文化が今でも息づいている、といった方が適切かもしれません。いくつかご紹介します。
目次
1:お辞儀は3種類
![]()
一言で、お辞儀と言っても、お辞儀の仕方によって意味が異なります。3種類に分けられていて、真(しん)行(ぎょう)草(そう)と言われています。
・真(しん):最も丁寧で正式なお辞儀
例えば、お茶会を始める前に亭主(ていしゅ:ホスト側)がみなさまに挨拶をする時など。
・行(ぎょう):真の次に丁寧なお辞儀
例えば、お客様同士での挨拶や、亭主が作法をしている際にするお辞儀など。
・草(そう):軽い挨拶程度の「会釈」に値する簡単なお辞儀
例えば、お点前の終わり頃にお客様から「どうぞお仕舞いください(終わりにしてください)」といったことを受けて、亭主が「お仕舞いにさせて頂きます(終わりにさせていただきます)」と挨拶する際など。
このように、お辞儀という行動でコミュニケーションの形があり、それぞれに適したやり方があります。
2:茶道のお点前は、相手に美しく魅せながら、合理的にお茶を作るように計算されている。
![]()
茶道のお点前といっても、やり方やその時によって細かいことは異なります。
しかし、基本的には、以下の点を抑えています。
・清潔であることを表す
・美味しいお抹茶を作るために努力をする
・汚れたものは極力相手に見せない
例えば、動作で言うと
・相手の目の前で、清潔だと見せるために道具を水に流す
・お抹茶を作る前にお茶碗を温めるため、お湯を通す
・きれいにするために流したお湯や水は、相手に見せないようにする
これらを全て、参加者であるみなさまの前で表現するのです。それは、数多くの練習をしなければ出来ないことです。
相手に楽しんでもらいたい、あなたを大切に思っている、そのために
努力を重ねてきたということを暗に表現できます。もちろん、招待をされたお客様もホスト側の様子を見守ります。
お互いに、大切に思い、それを表現することが茶道なのです。
3:お茶碗を2回半ほど回して飲む意味。
![]()
お茶碗をお客様にお届けする際は、お茶碗が一番華やかな面を相手に見せます。(お茶碗が一番華やかな面は、お茶碗の正面とします。)意味は、あなたを尊敬していますということ。
お客様側として相手からお茶碗を受け取ったら、お茶碗の一番華やかな面を自分からは避けます。そのために、お茶碗を2回半程度回すのです。意味は、あなたから尊敬されて恐縮です、という謙遜です。
無言のコミュニケーションであり、お茶碗の扱い方でそれぞれ「尊敬」と「謙遜」を表現します。
4:お抹茶を飲む前には、頭を下げる。
これは、すべてに感謝をするという意味が込められています。茶道では、色々なものや人が関わっているからこそ、成り立つものだと考えているからです。
例えば、抹茶を飲むということだけでも、たくさんのことが関わっています。
・抹茶を作る人、抹茶を点てる人
・お茶碗を作る人
・茶筅を作る人
・お茶の葉や水や火を作る自然、
・茶筅を作る人
など。あらゆる人やものがなければあり得ないのです。そのように考えて、すべてに感謝をすることで、より美味しくお抹茶を味わえます。
5:お抹茶を一気に飲む意味。
![]()
お茶碗のお抹茶は、基本的には一気に飲むことが基本です。なぜなら、それはお抹茶を点ててくれた相手に対して「あなたの作った抹茶は一気に飲み干すほど美味しいものです」という意思表示になるからです。
さらに、「ずずず!」と音を立てて飲むことで、より相手にそれが伝わりやすくなります。
6:季節やお茶会のテーマに合わせて相手を楽しませる。
さらに、茶道の道具は季節感を大切にしたり、お茶会で決めたテーマに沿ったもので取り合わせをします。
夏の時期には、出来るだけ暑さを感じさせない、フレッシュで、みずみずしさを表現できるような道具にします。
例えば、青と白の爽やかなデザインの茶道具であったり、夏らしさを表現したお菓子を用意します。冬の時期には、極力寒さを排除するための工夫や、ぽかぽかとした、あたたかさを演出するようにします。
例えば、椿といた冬を代表するお花を茶花にしたり、風炉と炉では、炉を使ったりします。お菓子は、もちろん年中使えるデザインのものもあります。
しかし、お菓子も四季を表現したものや、テーマに合ったものにすることで、より「相手を楽しませたい」という気持ちを表現できるのです。お菓子もお茶を飲む前にすべて食べることがマナーとされています。
それは相手が作ってくれるお茶を美味しく飲むためでもあり、お茶会をスムーズに進めるためでもあるのです。
また空腹の際に、突然抹茶のような刺激の強いものを胃に入れると荒れてしまうということもあります。このように、お客様側も相手の思いに答えるためにも、マナーを知り、実行していきます。
7:相手を大切に迎えるために特別な環境を整える。
![]()
茶室は清潔に、茶道の道具は季節やお茶会のテーマに合わせます。清潔感を大切にするため、きちんと掃除をします。
余計なものや生活感の出るものは極力排除して、非日常の空間を大切にするのです。それは、お互いに心地よい特別な空間で楽しむために準備をします。
その準備にかける思いも「あなたを大切に思っています」という表現になるのです。だからこそ、招かれたお客様側も清潔感を持った服装で参加します。
このように、茶道では「言葉を交わさずコミュニケーションを取る」作法、マナーによって成立しているところがあります。
もちろん、それはお互いに作法やマナーを知っているからこそ、出来ることです。
ゆえに、時には、作法やマナーを知らないことで「恥ずかしい」と思ってしまうこともあると思います。
私もそんな経験を沢山してきました。失敗して、恥をかいて、成長していきます。
ただし、私のお届けする「おもてなし茶道」のセミナーやお茶会では、初心者でも安心して参加できるようにしています。
分かりやすく、知っていると得する基本的な作法、歴史や作法も簡単にお伝えしています。
もちろん、着物も正座も必要ありません。リラックスして参加してくださいね!
あなたの毎日が茶道を通して、より豊かに、楽しくなりますように。